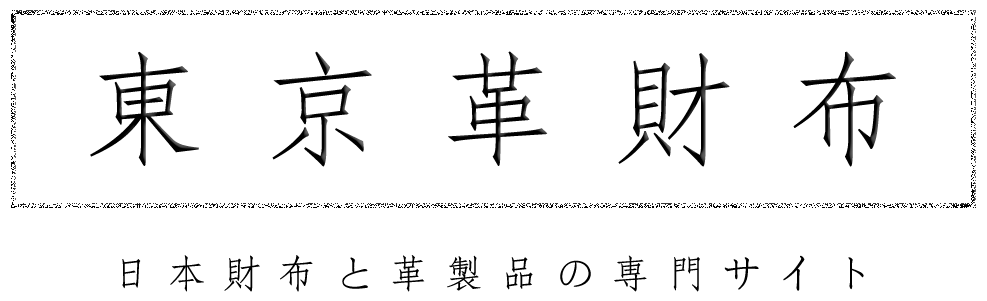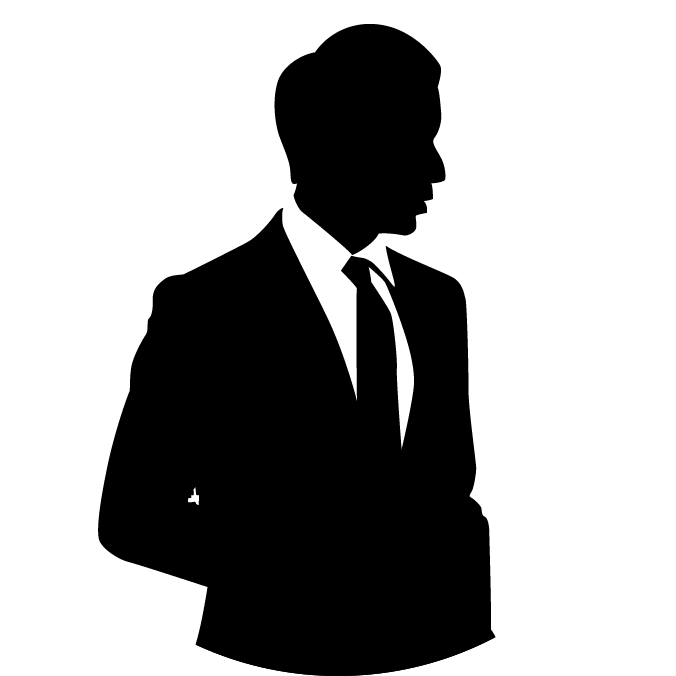「鞣す(なめす)」は革を作るための重要な工程。その方法によって革の特性や質感が大きく変わるのです。
この鞣しの方法を理解することで、革製品の選び方やその特性をより深く知ることができます。
今回は革の鞣しとは何か、鞣しの種類について解説していきます。
20代前半に土屋鞄製造所の革財布を購入し、革の魅力に目覚める。その後、WEBメディア事業主軸の会社に入社し、ライターからWEBディレクターまでを経験。革製品の魅力を広く伝えたいという気持ちが強くなり、2019年に独立して『東京革財布』を開設。これまで土屋鞄製造所、GANZO、CYPRIS、Hallelujah、SYRINXなど40種以上の財布・革製品を使用。豊富なレビュー経験とライタースキルを活かし、長く愛用してもらえる革製品と出会えるサイトづくりに努めている。
鞣すとは「皮から革」にするための作業

「鞣し(なめし)」とは、動物の皮を耐久性のある「革」に変えるための古代から続く技術であり、この工程を経ることで革製品の品質や特性が決まります。
動物の皮は、そのままでは時間とともに腐敗して硬化してしまうため、製品としての価値を持たせるための特別な工程が必要。その工程が「鞣し」というわけです。
この鞣しの技術は古代エジプト時代から存在し、その歴史と専門性は革製品の質を高める工程となっています。
この鞣しの工程を専門的に行う製造業者は「タンナー」と称され、彼らの技術と情熱が革製品の品質を支えています。
鞣しの種類とそれぞれの特徴
一言に「なめし」といっても、製法によって3種類に分けられます。
なめしの種類によって、仕上がる革の質感も違ってきます。鞣しごとの特徴を知り、レザー製品を選ぶときの参考にしてみてください。
【タンニン鞣し】古代から応用される植物成分のなめし

タンニン鞣しは植物から抽出したタンニンを使用する伝統的な鞣し方法であり、その特性から高級レザー製品に多く用いられる「王道レザー」の鞣し技術です。
タンニン鞣し、または「植物タンニン鞣し」とは植物の渋(タンニン)を主成分とする鞣し剤を使用する方法。この技術は古代から続く伝統的なもので、その特性から多くのタンナーが採用しています。
植物タンニン鞣しは古来より行なわれており、クロム鞣しが全盛を誇る以前はタンニン鞣しが主流であった。主に靴底革、中敷き革、ベルト用革、工芸用革などの製造に用いられる方法である。
※引用:日本比較技術協会「皮のなめし」
タンニン鞣しの特徴が次の通り。
タンニン鞣しは、その堅牢さや経年変化の美しさから高級レザー製品に多く見られます。特に、伸縮性が少なく丈夫な性質が求められる製品には最適です。
【クロム鞣し】化学成分をつかった量産型のなめし
クロム鞣しとは現代の革製品の大部分を占める鞣し方法であり、低コストで扱いやすいことから広く革製品に採用されています。
クロム鞣しは1884年に確立された比較的新しい鞣し技術で、「塩基性硫酸クロム」という化学成分を使用する方法です。この技術の導入により、革製品の製造が大量生産しやすくなりました。
クロムなめしで生産された革は、タンニンなめしの革に比べて弾力性があり、柔らか・滑らかで耐熱性(100℃超)や保存性、染色性も高いという特徴がありました。加えて1日で大量の革をなめすことが出来るため、製作コストの低減にもつながりました。
そんなクロム鞣しの特徴がこちら。
クロム鞣しのレザーは低コストなだけでなく、染色のしやすさからクロム鞣しの革は鮮やかな色合いが得られ、ファッションアイテムにも多く使用されています。
【混合鞣し(コンビネーション鞣し)】別の鞣しをかけあわせる方法
「混合鞣し(コンビネーション鞣し)」とは異なる鞣し方法を組み合わせることで、一つの革に複数の特性を持たせる技法。おもには、「クロム鞣し」と「タンニン鞣し」の2つの方法を組み合わせします。
基本的には“クローム鞣し”と“タンニン鞣し”のコンビが多いです。クローム鞣しの特徴である耐熱性や発色性、タンニン鞣しの特徴であるコシ感やエイジングといった双方の特徴を併せ持ちます。
クロム鞣しとタンニン鞣しの二つを組み合わせることで、クロム鞣しの鮮やかな発色性と、タンニン鞣しの経年変化のしやすさを一つの革製品に取り入れることが可能となります。
混合鞣しを施す順番や比率は、タンナーや製品の目的によって異なります。この技法を用いることで、従来の方法では得られない新しい質感や性質を持つ革製品が生まれるのです。
鞣しまでの皮革製造工程
なめしを含む皮革の製造工程は、実に多くの作業を要します。
ここからは、ポピュラーなクロム鞣しの製造工程をざっくり紹介。身の回りのレザー製品がどうやって作られているのか見ていきましょう。
※以下の参考写真は「日本皮革産業連合会」から引用。
①水漬け〜裏打ち

まずはじめに、皮についている血や汚れを落とすために水漬けします。皮を洗濯機で洗うようなイメージです。
ここでしっかり汚れを落とすことで、なめし剤といった薬品が浸透しやすくなります。
その後、細かな肉片や脂肪を落とす「裏打ち」という作業を行い準備完了です。
②脱毛〜分割

簡単な下処理が終わったら、以下のような工程に。
石灰乳につけることで皮のコラーゲンがほぐれるとともに、毛や余分な表皮が分解されます。必要な皮膚層だけ残るので、あの本革特有の柔軟性が生まれるというわけです。
石灰漬けの処理が終われば、加工しやすい大きさにカットしていきます。
③再石灰漬け〜浸酸
つづいてなめし剤を浸透させるための準備段階にはいります。
再び石灰漬けし、コラーゲン繊維の絡みをほぐします。また「酵解」という工程はタンパク質を分解する作業で、こうすることで革表面が滑らかに仕上がります。
最後に酸性溶液につける(浸酸)ことで、なめし剤を吸収しやすくします。
④鞣し

いよいよ鞣しの作業へ。なめし剤の入ったドラム槽やピットに皮を浸けて鞣していきます。
ここで鞣し剤と皮のコラーゲンが結合し、耐久性や耐熱性のあるレザーとなります。
⑤水絞り〜再鞣し
鞣しが終わると、なめし剤を洗い流し革の水分を絞り出していきます。また素材によってはこの段階で革の肉面を削り、決まった厚さにカットします。
その後、用途によって再なめし。同様のなめし剤を使うこともあれば、別の鞣し剤をつかって混合鞣ししていきます。
こうすることで製品に使える皮革へと仕上げられます。
⑥染色〜仕上げ

必要に応じて、染色や加脂を施します。脂を加えることで、革に柔軟性や滑らかさなどの感触が生まれます。
最後に革の余分な水分を絞り取り、乾燥させれば素材としての皮革の完成。その後は、製品ごとの大きさにカットしたりプラスの加工を施します。
革製品の購入時に「鞣し」もチェック
今回お伝えしたように、革の鞣し(なめし)とは生皮を加工して革に変える工程のこと。その方法によって革の質感や特性が大きく変わります。
革の鞣しには大きく分けて「タンニン鞣し」と「クロム鞣し」の2つの方法があります。タンニン鞣しは植物のタンニンを使用して行われる伝統的な方法で、経年変化を楽しむことができるのが特徴です。
一方、クロム鞣しは、クロムという化学物質を使用して行われる方法で、完成した革は柔らかく、耐久性にも優れています。
革製品を選ぶ際には、この鞣しの方法を理解することが製品の長持ちや使い心地を最大限に活かすカギとなります。